借入前に要チェック!金利と利息の正しい計算方法と返済の考え方
こんにちは!税理士の長岡です。今回は、「借入金利息の計算方法!」についての内容になります。最後までお読みいただけると幸いです。
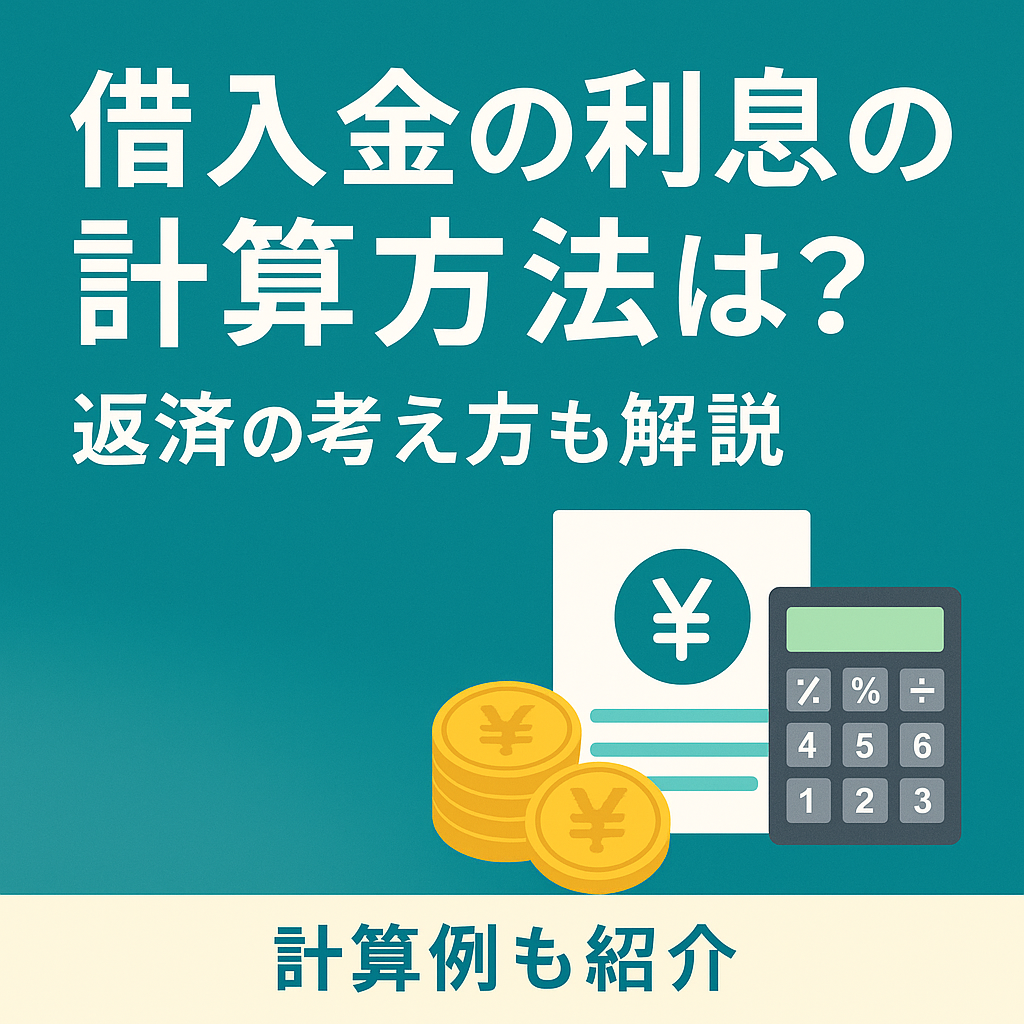
中小企業や個人事業主が運転資金を確保するうえで、借入は重要な資金調達手段です。しかし、実際に借入する際に「金利」「利息」「返済方法」の違いや仕組みを正しく理解していないと、思わぬ資金繰り悪化を招くことがあります。
本記事では、「金利の計算方法」から「シミュレーションツールの活用法」「返済計画の立て方」まで、借入における基礎知識をわかりやすく解説します。
金利と利息の違いを明確に理解しよう
- 金利(利率):借入金額に対して上乗せされる割合のこと。
- 例:金利3%で100万円借入 → 1年間で3万円の利息が発生
- 利息:実際に支払う上乗せ金額。
- 例:100万円借入 → 総返済額が110万円なら、利息は10万円
金利が「年〇%」と記載されていても、実際には日割りで計算されます。
利息の計算方法(実例付き)
利息 = 元金 × 年利率 ÷ 365日 × 借入日数
【例1】
2,000万円を年利2.5%で3年借入
→ 2,000万円 × 0.025 ÷ 365 × 1,095日(3年)
= 150万円の利息
【例2】
300万円を年利6.3%で5年借入
→ 300万円 × 0.063 ÷ 365 × 1,825日(5年)
= 約94.5万円の利息
返済方法の違いと選び方
借入金の返済方法は主に以下の3種類です。
■ 一括返済
- 返済期日にまとめて返済
- 利息が少なく済むが、資金繰り悪化のリスクあり
- 短期間の資金調達やつなぎ資金向き
■ 元金均等返済
- 毎月の元金返済額が一定
- 利息は初期に多く、徐々に減っていく
- 総返済額は少なめ
■ 元利均等返済
- 毎月の支払額が一定(元金+利息)
- 初期の利息負担が多い
- 総返済額は元金均等より多い
返済計画を立てるときのポイント
- 金利は「○%〜○%」と幅を持って表記される
- 高金利でシミュレーションしておくのが安全
- 長期返済ほど月額返済は少ないが、総利息が増加
- 安定したキャッシュフローがあれば繰上返済も有効
- 借り換えの際は、取引先との関係悪化に注意
シミュレーションツールを活用しよう
インターネット上には、借入金額・期間・金利を入力するだけで、毎月の返済額や総返済額を計算できる便利なツールがあります。
ただし、注意点もあります。
- 手数料や諸費用は含まれていない
- 実際の支払額は異なる可能性あり
- 最終確認は金融機関で!
経営判断としての借入と資金繰り
資金繰りを安定させるためには、借入そのものだけでなく、自社の財務状況を分析し、返済可能性を見極めた上での借入が必要です。
そのためには、経営者自身が財務数字を把握すること、そして必要に応じて専門家に相談することが非常に大切です。
【まとめ】
借入は資金繰りを支える重要な手段ですが、返済負担を見誤ると経営リスクに直結します。金利・利息・返済方法の仕組みを正しく理解し、計画的に借入を行いましょう。
当事務所では、借入シミュレーションのアドバイスから返済計画の立案まで、実務に即した支援を行っています。お気軽にご相談ください。
ホームに戻る